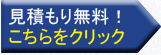2008年11月1日の良く晴れた日に、埋蔵文化財包蔵地の発掘現場に息子と見学会に行ってきました。
場所は、千葉県のJR津田沼駅の南西方500mぐらいのところです。
住居跡(正式には竪穴式住居跡)が、64軒も出てきたそうです。50cmぐらい地面を掘って、周りに盛り土して雨水を防ぎ、木で周りを土留めをして、生活していたとのことです。
縄文時代のものかと思ったら、ナント奈良時代だとのことで、 都会(平城京)と地方との格差を実感させられました。
下の写真が、一般的な住居の跡だそうです。 中央にある、丸くなっているところが、 かまどです。 ちょっと赤いのがお分かりいただけますですでしょうか。赤いのは火を使っていた証だそうです。

次の写真は土器がでてききた住居跡です。 リアルですね。

次の写真は、表土をはがした発掘前の状態です。 黒くなっている四角い部分がお分かりいただけますでしょうか? 自然な地層でないことから、住居跡と認識されるそうです。

この状態から、発掘作業が行われます。
案内してくれた人に聞いてみたのですが、一つの住居を発掘作業をするのに、4人がかりで、約1週間かかるそうです。
私は、埋蔵文化財と聞くと、直感的に、開発が遅れる、コストがかかるといったマイナスイメージしかなかったのですが、古の文化にふれるのもいいもんだなと思ったりしました。
え、息子ですか?
楽しんで見ておりました。小学生にも面白いんですかね!?